2020年12月23日
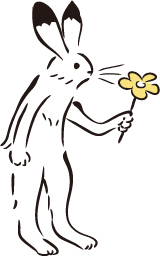
そう言えば、アレクサンダーテクニーク(AT)との出会いや、
「なぜATを選んだのか?」について、詳しく書いていなかったことを思い出しました。
せっかくなので、2020年が終わる前に書いておこうと思います。
ちょっと長いですが、ご興味のある方はおつき合いください。
どうしたら元気になれるんだろう?
プロフィールでも少し触れていますが、
私は30代後半に、心身ともに「絶不調」になりました。
(「プロフィール」を参照)
腰痛に始まり、音、ニオイ、人ごみなど
様々な刺激に敏感になり、日常生活に支障をきたすようになりました。
何もしていなくても、左腕がしびれることもありました。
当時勤めていた仕事も、続けられず辞めてしまいました。
「自分はどうしたら元気になれるんだろう?」と思い、
色々な体操や健康法の本を買ってきて試してみました。
でも最初「よさそう」と思っても、そのうち、飽きてやめてしまうのです。
なんか腑に落ちない、しっくりこないなぁと思っていました。
2つの疑問
何がしっくり来ていなかったのか?
まず、それらの方法の多くは、身体の特定の部位や、部分に特化したものでした。
骨盤が、足の裏が、指の先が、あるいはどこそこの筋肉が・・などなど。
当時は腰痛がひどかったので、腰痛対策を中心に試してみていたのですが、
改善は一時的なものでした。
ある程度は有効らしいとは思うのですが、根本的な解決になっていない気がしました。
そして何よりも「もっと全体的なことなんじゃないのかなぁ?」
という漠然とした疑問がありました。
骨盤や、足の裏が、身体全体に影響を与えているらしい、というのは理解出来るのですが、
実際やってみて全体のコンディションがよくなっている、という実感は
あまり得られませんでした。
なんだか浅い所をあちこちつつき回しているような気がして、
飽きてしまうのです。
「自分に今起きていることって、
もはや表面的な対策では間に合わないレベルなんじゃないだろうか?
もっと根本的な”何か”を変えないと、解決しないんじゃないだろうか?」
色々試すうちにそう思うようになりました。
これは殆ど直感と言っていいと思います。
「自分は崖っぷちだなぁ」とも思っていました。
* *
もう一つ私が引っかかっていたのが、「歪みを正しく直す」という考え方でした。
人間の身体の在り方に○×をつけるような捉え方って、自分にはどうも馴染まないなーと思ったのです。
生き物の身体って常に変化しているものだし、
「歪みを正しく直す」という考え方って、突き詰めると
「正しい身体は1つ!」ってことになっちゃうんじゃないかな?
それは違うだろう、と思いました。
これも私の直感です。
それならば、ケガをしたり、障害を持っていたリする場合は、
正しくない!と言えるのか?×をつけられるのか?
ケガや障害が重くて何年もその状態が続く場合、
その人はずっと「正しくない身体」という評価をされるのか?
それはなんかおかしいよな、と思いました。
よく、動物番組なんかで、
四肢のどこかが生まれつき無かったり、事故で失われてしまったりした動物たちが、
左右非対称だけど絶妙なバランスで活動していたりする様子を見かけますよね?
そこから考えても
「1つの静止画像的な規格」からはみ出た身体を、歪んでいる、正しくない、
と断定してしまう捉え方は、どうにもしっくりこなかったのです。
その後、気功や整体にも興味を持つようになります。
特に片山洋次郎さんの
「病気は経過するもの」という考え方にはとても共感しました。
(『整体から見る気と身体』/ 筑摩書房 より)
人間を全体として捉える。
症状をプロセスとして見ていく。
こういう考え方がベースにあり、
さらに仕組みがきっちりしているものはないだろうか?と思うようになりました。
私は原理や仕組みを知って納得したいタイプなのです。
気功や整体の考え方は、とても素晴らしいと思うのですが、
何分、目に見えない領域が多くを占めているため、
自分の性格から考えて、途中で投げ出してしまう可能性が高いなと感じました。
その後、書店で偶然手にした本が
アレクサンダーテクニークについての本でした。
「私が探しているものって、これかもしれない!」と思い、
たまたま開かれることになったワークショップを受けてみました。
崖っぷちに立っていた私。
「これかもしれない!」の直感は、
見事に当たりました。
探していたのはこれだ!
身体の使い方が変わると、楽器の音色まで変わる。
役者さんの声や在り方にも存在感が増していく・・。
ワークショップで初めて見た光景に私は驚きました。
また、外側から身体の形を変えるのではなく、
先生方の手によるガイド(ハンズオンと言います)に、私の身体が自然に応えて変化していく体験には、
人間に備わっている機能に対する大きな可能性を感じました。
・人間を部分ではなく全体として捉えている。
・歪みを「特定の正しさの枠」にはめこもうとするのではなく、
「今の状態から」自分をどのように使うのかを考えていく。
・今起きていることを「プロセス」として捉え、取り組んでいく・・。
ワークショップは限られた時間ではありましたが、
直感的に「これだな!」と感じました。
身体の使い方、心の使い方ではなく、
全てを統合した「自分の使い方」というコンセプト、そしてシンプルな原理は、
私がずっと探してきたものにピッタリだったのです。
さらに「特定の目的」限定のワークではなく、
自分が望むあらゆる活動に有効らしい、というところにも惹かれました。
ATが人生の目的そのものなのではなく、
あくまで「自分がやりたい活動」の
手段・架け橋として助けになってくれるのなら、
それこそが私の望んでいるものだったからです。
これが私とATとの出会いでした。
今から約11年前のことです。
(2020年12月現在)
私の10年計画 (介護職に就いたわけ)
当時、まだ無職でした。
私は、アレクサンダーテクニークの教師養成学校へ入るまでの
計画を立ててみました。(まだどこの学校へ入るか・・とかは、決めていない状態でした。)
「これは10年計画だな」と思いました。
「教師になりたい!」というよりも、
「徹底的に取り組みたいものに出会ったぞ!」という方が、
動機としては強かったと思います。
実際、決めてから入学するまでに7年かかり、
教師養成トレーニングが約3年でしたので、
計画通り、教師になるまでにバッチリ10年かかっています。
自分で考えた計画の「最初の一歩」は
なんと職業訓練でヘルパー2級を取得し、介護施設(老健)で働くことでした。
調べてみて知ったのですが、
老健(介護老人保健施設)は、リハビリをして在宅復帰を目指す施設ということでした。
元々、ことの発端は、
「自分はどうしたら元気になれるのか?」という自分への問いでした。
それならば、人が元気を取り戻す現場を見てみたい。
そこで人の心身に触れる経験を積みながら、入学資金を貯めればいいんじゃないか?
そう思ったのです。
さらに、介護現場で働きながら、お休みの日は習い事としてATを学んでみよう。
ATはきっと、働く自分の助けにもなってくれるだろうから・・。
なにより、とっても楽しそう!
いつの間にか、私の「崖っぷちの絶不調」は、
単なる憎むべき症状、病ではなく、
自分のよりよい使い方を探究する第一歩となっていました。
* *
私の場合、ATと出会うまでが長かったのですが、
「なぜATを選んだのか?」については、結構大事なことだなと思っているので改めて書いてみました。
少しでもご参考になることがあれば、うれしいです。

![]()
![]()
![]()
ATを学び始めてからの変化については、こちらをご参照ください。
「私の変化」のブログをまとめました。